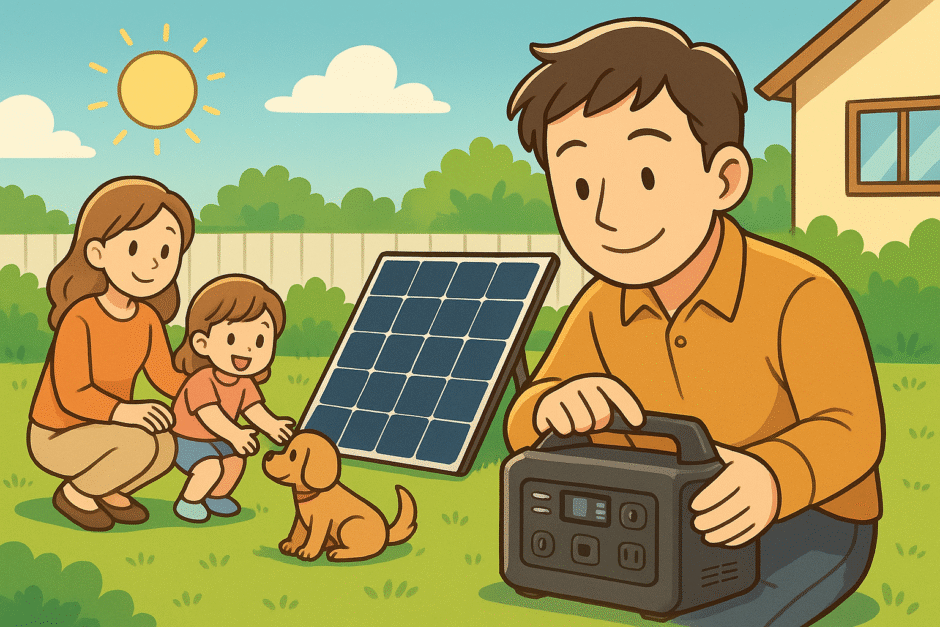※アフィリエイト広告を利用しています。
はじめに
こんにちは、中年パパの子育て研究所です。
先日、父から「防災用に」と渡された持ち運びサイズのポータブル電源。
しばらく押し入れにしまったままだったのですが、久しぶりに開けてみて驚きました。
「これ、めちゃくちゃ便利じゃん…!」
軽くて、太陽光パネルでも充電できて、しかもLEDライト付き。
まさに“防災 × アウトドア”の両方で使える優秀アイテムだったんです。
今回はそんな体験をもとに、
**「家庭に1台あると安心なポータブル電源」**について、
パパ目線でリアルに紹介していきます。
結論:ポータブル電源は「防災の安心」と「外遊びの自由」を両立する
結論から言うと、
ポータブル電源は「備え」だけで終わらない道具です。
✔️ 災害時の停電対策として
✔️ キャンプやピクニックなど、子どもとのお出かけに
✔️ 家族のスマホやタブレットを同時充電できる
つまり、“いざという時も日常も支えてくれる電源”。
使ってみて初めて、そのありがたみを実感しました。
なぜポータブル電源を選んだのか
きっかけは、父からの一言でした。
「これ、防災用に持っておけ。」
正直そのときは「そんな大げさな…」と思っていました。
でも3歳と0歳の子どもがいる今、**“もし停電したら”**と考えると背筋が冷たくなります。
・スマホが使えない
・冷蔵庫が止まる
・夜の灯りもない
そんなときに、持ち運びができる電源が1つあるだけで心の余裕が全然違う。
実際に開封してみて、その価値を実感しました。
メリット:持ち運び電源のここがすごい!
① 軽くて扱いやすい
思っていたよりもコンパクト。
妻でも片手で持ち運べる重さで、リビングや車の中にもすっきり置けます。
② 太陽光パネルで充電できる
もし停電が長引いても、ソーラーパネルで電気を“作れる”安心感。
家庭用コンセントが使えなくても、外で充電して再利用できるのは心強いポイント。
③ LEDライト付きで非常灯になる
停電時はもちろん、夜のキャンプや車中泊でも大活躍。
デメリット:もちろん弱点もある
① 容量が限られる
小型タイプは、スマホやタブレットの充電がメイン。
電子レンジや炊飯器など、電力の大きい家電は動かせません。
ただ我が家では、3kWhクラスの大容量蓄電池も別に導入しているので、
小型タイプと組み合わせて“相互補完”できる体制にしています。
ちなみに、災害時に特化するなら「太陽光+蓄電池」の組み合わせが最強です。
電気を“貯める”だけでなく、“作れる”仕組みがあると、本当の安心につながります。
② 出力の制限
出力が120W程度だと、ノートPCや小型家電がギリギリ。
もし家全体の電源をカバーしたいなら、上位モデルを検討すべきです。
我が家のリアル体験:実際に使ってみた感想
久しぶりに電源を入れてみたとき、
「え、こんなに静かで軽いの?」と驚きました。
LEDライトを点けてみると、想像以上に明るく、
夜中に子どもが泣いたときにも**“非常用ライト”としてそのまま使える**レベル。
まだ災害時には使っていませんが、
スマホ・タブレットの充電はまったく問題なし。
これ1台あれば、停電中でも子どもの動画や連絡手段が確保できます。
正直、テンションが上がりました(笑)。
他製品との比較:大容量との使い分けがカギ
ポータブル電源にはいろいろなタイプがありますが、
我が家のおすすめは**「小型+据え置き型の2台持ち」**です。
| 用途 | おすすめタイプ | 例 |
|---|---|---|
| 緊急時・持ち出し | 小型・軽量タイプ(出力120W〜) | クマザキエイムなど |
| 家庭用バックアップ | 大容量タイプ(2〜3kWhクラス) | Jackeryなど |
このように使い分けることで、
「日常 × 防災」をどちらもカバーできます。
まとめ:子育て家庭こそ“電気の備え”を
子どもが小さい家庭では、
電気=安心そのもの。
ポータブル電源が1台あるだけで、
・夜間の不安
・通信手段の途絶
・冷暖房の停止
といったリスクを大幅に減らせます。
そして何より、
普段のキャンプや公園遊びでも「電源がある安心感」は心を軽くしてくれます。
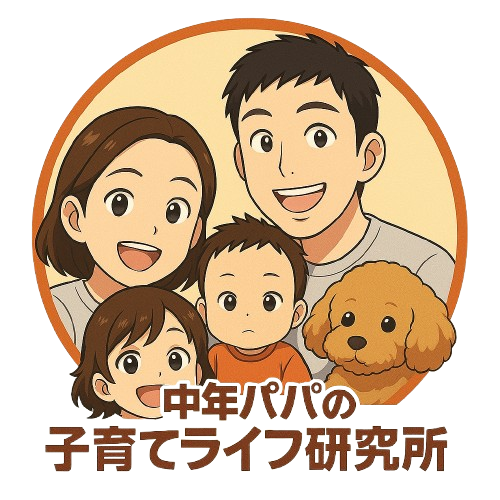 中年パパの子育てライフ研究所
中年パパの子育てライフ研究所