※アフィリエイト広告を利用しています。
こんにちは、中年パパの子育て研究所のイトウ ヒロシです。
今回は「家庭用蓄電池って本当に必要なの?」というテーマで、
実際に我が家が購入したリアルな体験をもとにお話しします。
正直、買う前は「本当に使うのかな?」と半信半疑でした。
でも、子どもを持つ家庭にとって“電気の備え”は、想像以上に大切なものでした。
結論:子育て家庭には“在宅避難”+蓄電池が最適解
まず結論から。
災害時、子育て世帯が避難所で生活するのは、かなりのストレスです。
テレビでよく見る避難所の映像。
実際には 1人あたり約1畳ほどのスペース しかなく、プライベート空間はほぼゼロ。
子どもが泣いたり、遊んだりするたびに周囲に気を使ってしまう現実があります。
そのため、国交省は「在宅避難」を推奨 しています。
避難所はあくまで最終手段。できるだけ自宅で生活を続けることが望ましいと明言しています。
在宅避難を実現するために必要なのは、
【①食料】【②水】【③電気】の3つ。
中でも“電気”の確保が最もハードルが高く、重要です。
在宅避難に欠かせない“電気の確保”
今の生活は、冷蔵庫・スマホ・照明・給湯器など、
ほとんどが電気に依存しています。
つまり、停電=生活停止。
真冬に停電したとき、子どもたちをどう守るか?
そう考えると、電気の備えの大切さを痛感しました。
そこで購入したのが、ポータブル蓄電池 Jackery(3000Wモデル)。
モデルチェンジのタイミングで 半額 になっていたこともあり、思い切って購入しました。
我が家で感じたポータブル蓄電池のリアル
1. 想像以上に“大きい”
届いた瞬間、「これ、どこに置こう…?」と思うほどのサイズ。
コンパクトな見た目を想像していた分、かなり存在感があります。
2. “重い”
大容量モデル(3000W)ともなると、かなりの重量。
ママが一人で持ち運ぶのは難しく、どこに設置するのか設置場所を考える必要があります。
3. “収納スペースに悩む”
最大の課題がこれ。
「災害時にすぐ取り出せる場所」と「邪魔にならない収納場所」は両立が難しく、
我が家では正直…ダンボールのまま放置中(笑)。
でも、どこかにあるだけで“安心感”が違います。
まるで家族の保険のような存在です。
太陽光+蓄電池が理想。でも我が家は…
わが家は住宅の構造上、太陽光パネルを設置できません。
そのため、今回は ポータブル蓄電池単体 の備えを選びました。
もし太陽光が設置できるのであれば、
「太陽光+蓄電池」こそ最強の防災コンボ です。
昼間の発電を夜に使うことができ、
停電時でも冷蔵庫や照明を維持可能。
実際、国(環境省・経産省)もこの組み合わせを推奨しています。
また、「太陽光+蓄電池」であれば電気代の削減効果も期待できる為、
その削減効果を鑑みれば導入費用はほとんどかからないことになります。まさに最強。。。
子育て家庭にこそ「電気の備え」が必要な理由
子どもがいる家庭では、停電の影響はより深刻です。
例えば…
- ミルクをつくるためのお湯が沸かせない
- 夜間の照明がないと子どもが不安になる
- スマホの充電が切れて情報が得られない
そんな時、ポータブル蓄電池があれば安心です。
・スマホの充電
・電気ポットでミルクづくり
・小型ヒーターの稼働
など、最低限の生活を守ることができます。
購入前に知っておきたい注意点
- 思ったよりも大きく重い
- 保管場所を決めておく
- 定期的な充電メンテナンスが必要
特に3つ目は盲点。
いざという時にバッテリーが空では意味がありません。
我が家では、月に1回の「動作確認デー」を設けようと考えています。
おすすめのポータブル蓄電池メーカー
もしこれから購入を検討するなら、信頼できるメーカーを選びましょう。
| メーカー名 | 特徴 | 価格帯 |
|---|---|---|
| Jackery(ジャクリ) | 防災&アウトドアの定番。操作がシンプル。 | 中〜高 |
| EcoFlow(エコフロー) | 大容量&急速充電対応。デザイン性も◎ | 中〜高 |
| BLUETTI(ブルーティ) | 長寿命バッテリー搭載でコスパ良し | 中 |
まとめ:在宅避難は“家族の安心”をつくる準備
避難所に行くことが「避難」ではなく、
自宅でどう生き抜くか を考える時代です。
子どもたちの安心と安全を守るために、
食料や水と同じように「電気の備え」も考えてみてください。
ポータブル蓄電池は、
“もしもの安心”を買うための一つの選択肢。
我が家では、今後キャンプなどをする時の電源として使用を検討しており、
災害時だけではない使い方も視野に入れてワクワクしています。
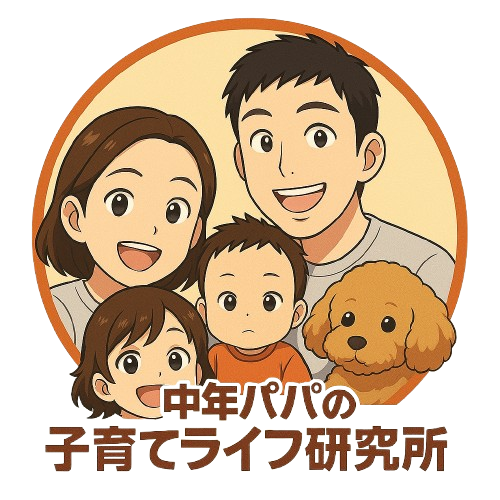 中年パパの子育てライフ研究所
中年パパの子育てライフ研究所 


